どうも、コイヌマ( @koichan8888 )です♪
前回、自分の優柔不断なところや、意志の弱さ、精神力の弱さなどの原因が理解できるヒントになり、対策も取れるということで役立つかもしれないということを書きました。
実際に、自分自身も、この考え方を取り入れてからは、すごく行きやすくなりましたし、考え方のレパートリーが増えたなぁと思っています。
今回は、前回に引き続き、ポール・マクリーン博士の3つの脳の層構造「三位一体脳」論について考えてみたいと思います。
前回の記事を読まれていない方は、ぜひ読まれていただければ嬉しく思います。
爬虫類、哺乳類、人間脳への進化

内側の部分から
1.爬虫類的脳(脳幹)
脊柱から直接発言し、いわゆる本能的な反応を司ります。
呼吸や心臓の鼓動を維持したり、敵にあった際の「逃走と逃走の反応」など原始的な本能をコントロールします。
ボクたちは、誰かにあまりにも近く寄られると、怒りや不快感を覚えるのは、この爬虫類脳の性質によるものです。
2.哺乳類的脳(大脳辺縁系)
視床下部や脊柱を始めとする器官を含み感情や性的発動や快楽中枢を司る脳の事です。
ホルモンのシステムや、免疫システム、セックス、感情、それに長期記憶などの重要な部分を担っています。
3.人間的脳(大脳新皮質)
いわゆる思考を司るのが、この部分で、論理的思考や数学的思考など知的なプロセスを司ります。
これら3つの脳の部分が「爬虫類⇒哺乳類⇒人間」と進化の順番を経て、本能的反応の段階から感情的反応や記憶の発生を経て、新しい脳、つまり人間的、大脳新皮質へと複雑な段階へと至る進化を示しています。
これが、「三位一体脳」という概念です。
極めてシンプルに言えば、
- 本能的な爬虫類脳
- 感情的な哺乳類脳
- 論理的な人間脳
という分類も出来るわけです。
確かにポール・マクリーン博士のこの脳の三層構造という説は、厳密なモデルとして
学術的に認められている訳ではないのですが、ボクたちの日常生活において、極めて役に立つ概念だといます。
特に重要なのが大脳辺縁系

そして、右脳と左脳だけでなく、この三つの脳を意識して学習を進めて行くと大変効果的な結果を得ることが出来ます。
三位一体脳の中でも、特に、哺乳類的脳の大脳辺縁系のコントロールが重要になってきます。
そして人間脳をうまく使いこなせるかにかかっています。
動物で人間だけが、ロジックで物事を考えたり理性を持って長期的に考えたり、分析力を持っています。
しかし、それを邪魔する事もあるのです。
嫉妬心が計画をじゃましたり、試験勉強中についついお菓子を食べすぎたり、異性が気になって集中できなかったり、ボクたちの衝動的な部分をいかに理性的な思考へ移行させるか、そういった役割を果たすので非常に重要として注目されています。
一つ一つの脳の層が独立しているのではなく同時に働く三層構造なのです。
だからこそ人生は素晴らしいものになり、同時に失敗をやらかしたりもします。
こうした機能は、理解しておけば、学習や仕事にも上手く活用できます。
脳は、いくつになっても鍛えられる
右脳・左脳もそうですし、こうしたポール・マクリーン博士の提唱する3つの脳の層構造「三位一体脳」論のように脳は部位によっては働きが異なります。
そして脳が、筋肉や皮膚の情報を司る末端神経の情報を受け取り、筋肉を動かすように身体の各部分に情報を送ったりと、まさに司令塔のような役割を担う臓器なのですが、そのなかでは「ニューロン」と呼ばれる約200億とも1000億個とも言われるおびただしい数の脳神経細胞から構成されているのです。
この脳を構成するニューロンは20歳を過ぎたあたりから確かに減って行きます。
そして死滅したニューロンは再生しないと長年考えられてきました。
年を取ると記憶力が落ちるのは、その為だと考えられていたのです。
しかし、ニューロンはその数ではなく、繋がりによってその強さが決まります。
いつまでも頭を使う事で、ニューロンの結びつきは強化できるのです。
さらに最近の研究では、脳の使い方次第によっては加齢によってもニューロン自体が増えるという報告もなされています。
そんな感じで、脳がめちゃくちゃ偉大であるし、脳のことについて学ぶと面白いヒントがいっぱい隠されているということを知ったのでした。
では、実際に「三つの脳を活性化させることはできるのか?」について次回の記事でまとめて見たいと思います。
それでは。




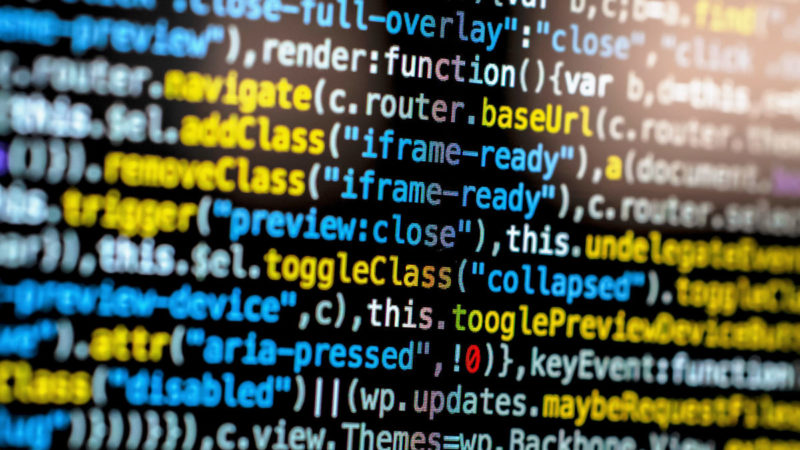
コメント